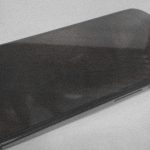視界

恵比須顔の老婆
嗚呼、もうこんな時間かと時計を見、伸びをして欠伸をひとつし、いそいそと床に入っていた時が懐かしい。
それが今や、まともに眠れる事はない。安心して眠れるのであれば、全財産を差し出しても惜しくはないが、その財産なんて高が知れてる身では、神も端っから見放してるようだ。
いつからあれが見えだしたのか、定かではない。ただ見えるとはいっても、目を瞑った後の瞼の裏にあれが、奇妙な現実感をもって現れるため、本来の見えるとは異なるのだろう。
相談した何人かには「夢でしょう」と軽く流され、また何人かには「錯覚だ。頭ん中のものが目の前にいるよう感じただけ、目を瞑っていては見えるものも見えない」と言われ、ある連中には「先祖の業が」などと言われた。
多分、あれが見える、現れる以前は、目を瞑って物事をあれやこれと人並みに考えたこともある。だから、その違いは分かっている。でも、どうしても他人にはこの違いが伝えることが出来ず、伝わらず、やがて相談することを止めた。
瞬きは問題ない。目を瞑って十ばかりゆっくりと数えると、ぼろを纏った恵比須顔の老婆が視線の先に現れて、ゆるりゆるりと迫ってくるのである。
そしてある時、どういったわけか、いつもと違って老婆が眼前まで到達した。
老婆は恵比須顔のまま二本の細い腕を突き出した。その動きを目で追っていると、刹那、吃驚するような力で掌が首に絡みついた。さらに現実感を伴う苦しみが身体を駆け巡った。老婆の手首を掴んで、なんとか引き剥がそうとしたが埒が明かないので、老婆との間に右足をねじ込むと、左足を踏ん張り右足を思いっきり伸ばした。
そこで覚醒した。首はひりひり痛み、老婆の手が掛かっていたであろう部分は、強引の引き剥がしたせいで爪が立てられたのであろう、血が滲んでいた。暫くは恐怖に震えが止まらなかった。
それ以降、何年、もしかしたら何十年にもわたって何度となく同じ状況に陥っている。その結果、睡魔に従って床に入ることは一切なくなった。睡魔を振り払い眠くても寝るのを我慢し、「無意識のうちに落ちる」ことでしか老婆を回避できないからだ。僅かでも自らの意志で目を瞑ると、あの老婆が現れる。
一時期は、見なくて済むように両目を潰しては、という発想に至ったが、目を潰す事と目を瞑る事は同じ闇をもたらすのではないかと思い至り、やり直しが利かない以上諦めた。それでも、ナイフをこの目に突き立てたい衝動が時々湧き起こる。
老婆が現れても、眼前に来る前に目覚める事があるにはあるが、その頻度は徐々に低下しており、その“猶予”がなくなるのは間近だと分かっている。
あの恵比須顔の老婆は一体何なんだ。気が狂いそうだ。いや、もう狂っているのかも知れん。狂っているからこそ、あんなものを見るのだろう。しかし、どうしようもない。
煙草のありかを探り当てると、一本取りだし、慎重に吸い口を確かめ火を付けた。
眠りたい、眠りたい。本当に眠りたい。ただ、それだけだ。
これはフィクションです